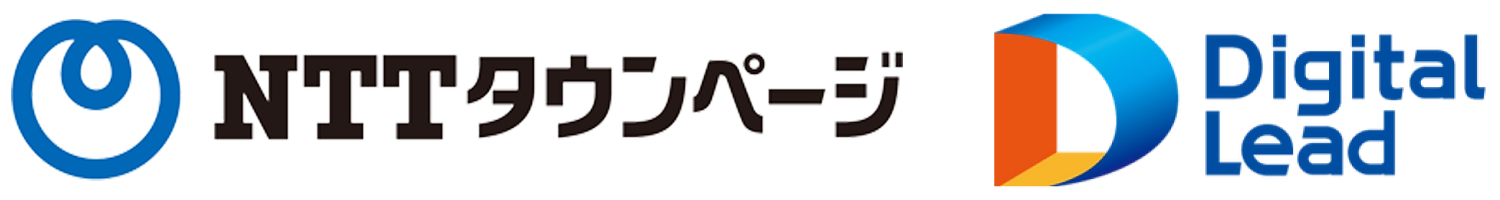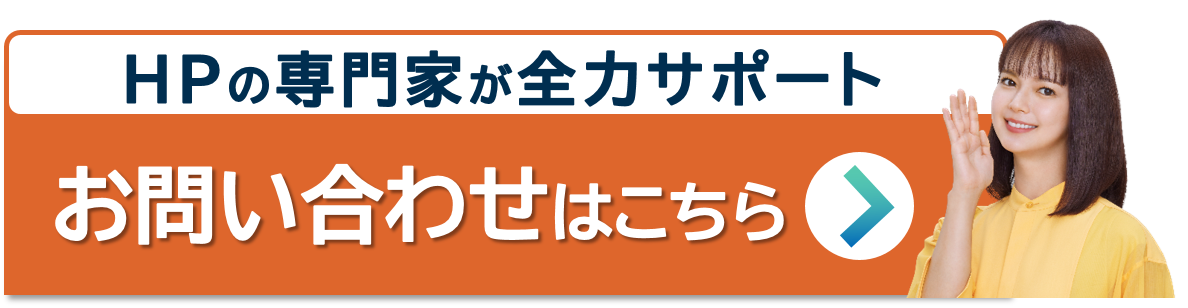アクセシビリティという言葉は、英語の“Accessibility”から来ていて、「近づきやすさ」や「利用のしやすさ」を意味します。要するに、誰もが平等に情報やサービスを使えるようにすることが大切です。最近では、すべての人が情報通信の世界にアクセスできるように、ホームページやアプリでもアクセシビリティが求められています。それでは、私たちがどのようにその環境を作っていけるのか、一緒に見ていきましょう。
アクセシビリティの基本概念
アクセシビリティとは何か?
アクセシビリティは、すべての人がサービスや情報に簡単にアクセスできることを指します。特に高齢者や障がいを持つ人にとって、使いやすい環境が必要です。これにより、身体的な障壁を超えて、誰でも平等に情報通信サービスを利用できるようになります。
アクセシビリティが重要な理由
アクセシビリティは、みんなが情報を得る権利を守るために必要不可欠です。誰もが情報にアクセスできれば、より多くの人が社会に参加できるようになります。例えば、災害時に必要な情報がすぐに得られることは、命を守るために非常に大切であることから、アクセシビリティは重要なのです。
どうやってアクセシビリティを確保するの?
ホームページを作る際には、アクセシビリティの観点からも色使いやフォント、レイアウトに気を配ることが必要です。また、音声読み上げ機能や代替テキストを活用することで、視覚障がい者でも情報を得やすくするアクセシビリティが求められます。
ユニバーサルデザインとアクセシビリティ
ユニバーサルデザインとは、すべての人が使いやすいように設計されたものを指します。これには、高齢者や障がいのある人が特に使いやすくなるような工夫が含まれます。たとえば、電車のホームにある点字ブロックや、スロープなどがその例です。
アクセシビリティは、特定のニーズを持つ人に配慮した設計を指します。この2つはめざすゴールが同じですが、アプローチが異なります。具体的な例としては、色覚異常の人のために、色だけではなくテキストでも情報を提供することが挙げられます。
【アクセシビリティに配慮した製品の例】
・大きなボタンの携帯電話
高齢者が使いやすいように、ボタンが大きく設計されています。これにより、視力が弱い方でも簡単に操作できるので安心です。
・音声読み上げ機能付き携帯電話
メールやメッセージを音声で読み上げてくれる機能があります。視覚に障がいのある方にとって、非常に便利な機能です。
ウェブアクセシビリティの重要性
ウェブアクセシビリティとは?
ウェブアクセシビリティは、ホームページやアプリがすべての人にとって使いやすくなっているかを意味します。特に視覚や聴覚に障がいがある人、高齢者など、さまざまな人が情報やサービスにアクセスできることが重要とされています。
ウェブアクセシビリティが必要な理由
今の時代、ホームページは情報を得るための重要な場所です。特に高齢者や障がいのある人にとって、必要な情報が得られないと生活に困ることがあります。たとえば、災害時に避難情報が分からないと、命にかかわる問題が発生する可能性があるため、ウェブアクセシビリティを意識したホームページの構成が必要となります。
ウェブアクセシビリティ設定方法
ウェブアクセシビリティのためには使いやすいメニューや明確な色のコントラスト、画像に代替テキストをつけることが基本です。また、W3C(World Wide Web Consortium)が出しているWCAG(Web Content Accessibility Guidelines)に沿って作るといいでしょう。
※WCAG(Web Content Accessibility Guidelines):ウェブサイトやウェブコンテンツができるだけ多くの人に公平に利用されるために設けられた国際的なガイドライン
【ウェブアクセシビリティの具体例】
ウェブアクセシビリティを意識したホームページを作るときに気をつけるポイントをいくつか紹介します。
・メニューを分かりやすくする
難しい言葉は避けて、誰でも理解できる言葉を使うことが大切です。「お知らせ」や「サービス」といった言葉を使うと、分かりやすくなります。
・サイトマップを作る
サイト全体が見えるように、目次(サイトマップ)を用意します。これによって、利用者は必要な情報を簡単に見つけることができます。
・代替テキストを使う
画像には説明文(代替テキスト)をつけて、視覚に障がいのある方が内容を理解できるようにします。たとえば、グラフの画像にはテキストによるデータの説明を入れるといいです。
ウェブアクセシビリティで配慮すべきこと
ウェブアクセシビリティがなされているホームページを作るときは、利用者の視点で考えることが大切です。利用者がどんな状況にあるかを想像しながら、どうしたらもっと使いやすくなるかを考えましょう。具体的には、先ほどのウェブアクセシビリティの具体例に加えて以下のポイントに注意することが重要です。
・色の使い方を見直す
文字と背景の色の組み合わせが見やすいか確認しましょう。たとえば、白い背景に黒い文字は、視認性が高くておすすめです。逆に、緑と赤の組み合わせは、色覚に障がいのある人には見づらいので注意が必要です。
・フォームをわかりやすくする
入力フォームでは、必須項目を明確に示し、エラーメッセージもわかりやすく伝えることが求められます。利用者が入力ミスをしたときに、どこが間違っているかをはっきりと伝えることで、スムーズに修正できます。
・テストをおこなう
実際に自分以外の人にホームページを使ってもらい、使い勝手を確認しましょう。特に高齢者や障がいのある人にフィードバックをもらうことで、思いがけないウェブアクセシビリティにつながる改善点が見つかるかもしれません。
これらのポイントを意識することで、すべての人が使いやすいホームページを作ることができます。小さな工夫の積み重ねが、誰にとっても優しい環境を生み出す大きな一歩になります!
今後の展望について
2024年4月1日から、改正された障害者差別解消法が施行されます。これによって、民間企業やお店も障がい者に対して「合理的配慮」を提供することが法律で義務付けられます。これまでは主に行政機関がこの配慮をおこなう必要がありましたが、これからは企業も同じように配慮することが求められるのです。
この改正の背景には、障がいについての考え方が変わってきていることがあります。昔は障がいは「個人の問題」と捉えられていましたが、今は「社会の中にあるバリア」の問題として考えられています。つまり、障がいがある人が直面する困難は、社会が作り出しているものであり、みんなで解決していくべきだという考え方です。
具体的には、企業やお店は、障がい者からの「このように配慮してほしい」と要望があった場合、負担があまり大きくない範囲でその要望に応えなければなりません。これには、物理的な環境を整えることや、コミュニケーションの方法を工夫することが含まれます。
この新しい法律が施行されることで、より多くの障がい者が日常生活や社会活動に参加しやすくなります。すべての人が平等に利用できる社会を目ざして、私たちもこの変化を大切にし、アクセシビリティを高めるための取り組みを進めていくことが必要です。
以上のとおり、アクセシビリティとは、すべての人がサービスや情報に簡単にアクセスできることを指しています。特に高齢者や障がいを持つ人にも使いやすい環境づくりが重要視されていますので、利用者の視点で改善を続け、誰にとっても使いやすいホームページの実現が求められています。
NTTタウンページでは、ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」をご提供しています。
2019年のサービス提供開始以降、累計40,000件を超えるホームページを制作・運用し、個人事業主、中堅・中小企業をはじめとした多くのビジネスオーナーさまにご利用いただいてきました(2024年10月現在)。
これまで培ってきたNTTグループの知見とノウハウを活かして、多種多様なサービスと充実のサポート体制で、忙しいビジネスオーナーさまのホームページ制作から公開後の運用に至るまで、責任を持ってサポートいたします。

ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」の特長
特長①
ホームページ制作・運用はNTTグループの専門スタッフがフルサポート!
特長②
さまざまな目的のホームぺージ制作に対応、デザインも洗練!
特長③
ネットショップ・予約機能など、ホームページでの成約に導く充実機能多数!
ホームページは「制作して終わり」ではなく、その後の集客や売上アップなど目的とする「成果」につなげてこそ価値があります!
「インターネット・Webが苦手なのでサポートしてほしい…」
「競合に”勝てる”ホームページをめざしたい」
など、当社は全てのビジネスオーナーさまのホームページ活用に関するお悩み・課題に寄り添い支えます。
ぜひ、あなたのホームページの全てをお任せください!
ホームページの基礎知識に関連する記事