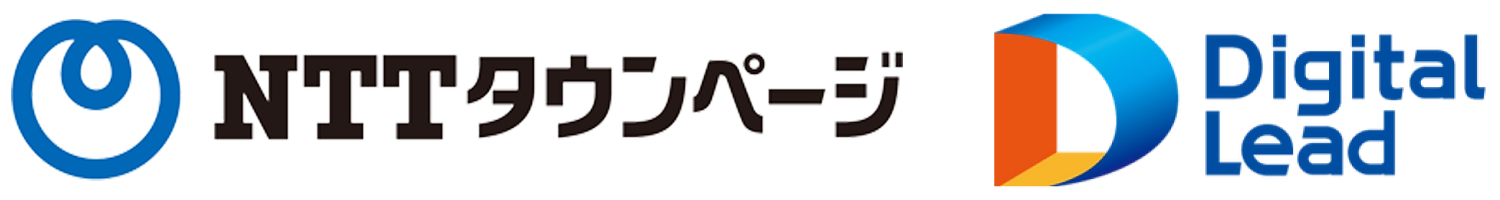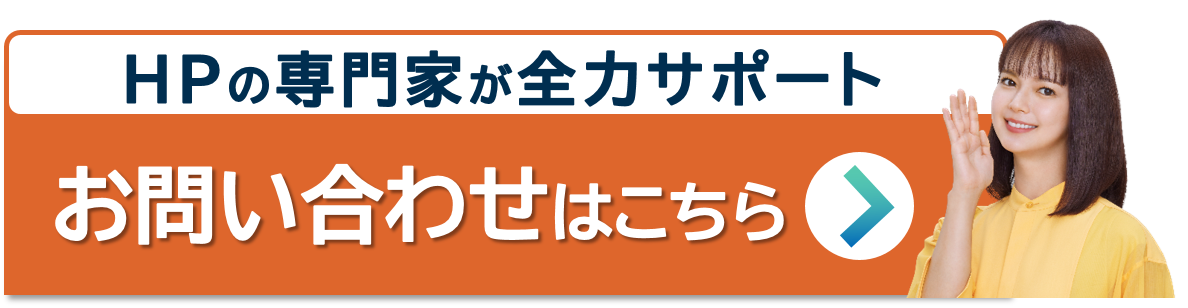ビジネスオーナーがホームページを活用し、商品やサービスを紹介することで集客やお問い合わせにつなげるための「テクニック」の一つに、Webライティングがあります。
お客さまからの商品購入・お問い合わせにつなげるために、ホームページに掲載する記事(以下、コンテンツ)で「文章はこれでいいかな?」「こういう書き方で伝わるかな?」「ここまで盛りだくさん載せて大丈夫かな?」と悩み多きビジネスオーナーも少なくないのではないでしょうか?
本ページでは、Webライティング全般におけるコンテンツ閲覧時のユーザーの心理、Webライティングを掲載する時の注意点・対策について解説します。
また、ホームページにおける2種類の「ライティング」については以下の通り区別します。
コピーライティング:ホームページやインターネット上の広告における文言やキャッチコピーを作成する技術
Webライティング:ホームページやブログなどのコンテンツを作成する技術
コンテンツ閲覧時のユーザーの心理
ユーザーがキーワードでホームページを検索してページにたどり着いた時の心理としては、以下のようなものが想定できます。
- 早く自分の希望や好みに合ったものを見つけたい
- 品質やサービス内容がちゃんとしたものを見たい
- 自分にメリットがあるものがいい
- しつこい広告は嘘っぽい、煩わしいから嫌だ
お客さまがホームページを開いて3秒程度見た時、こういった心理にそぐわないものだったらどうなるでしょうか?
少しでも「自分には合わない」、「メリットを感じない」と感じたら、すぐに離脱して、別のホームページを探しに行きます。さまざまな情報があふれるインターネットの世界で大抵の場合、こういった理由で離れたホームページに再びユーザーが戻ることは無いと言っていいでしょう。
Webライティングを掲載する時の注意点
ホームページのコンテンツは、公開した瞬間から世の中に出ます。
ここでは注意すべきポイントを紹介します。
お客さまに「興味を持ってもらう」コンテンツになっているか?
お客さまにメッセージを伝えて商品やサービスを覚えてもらい、さらに商品購入・お問い合わせにつながる行動へつなげるために、時にはお客さまの立場に立って共感を呼ぶ言葉や、購入を誘うコンテンツを編み出す必要があります。
「次を読もう!」と思わせる内容が掲載されているかを念頭に置いてコンテンツを読み返してみましょう。
法律的に問題ないか?
興味を持つようなコンテンツを意識すると「こんな商品があります!」「こんなサービスが可能です」など、お客さまへの訴求に目がいきがちですが、何でも載せていいというわけではありません。
掲載に関連する主な法律は以下の通りです。
・景品表示法(景表法)
実際よりも良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われることを防止する法律
・不正競争防止法
レイアウトや構成を模倣する、素材(文章、画像、イラストなど)を模倣する、他社のホームページになりすまして営業することを防止する法律
・医薬品医療機器等法(薬機法)
旧薬事法とも呼ばれ、効果や安全性を保証する表現や、根拠のない効能を謳うことは違法となるため、必ず事実に基づき適切な表現を心がける必要がある
・著作権
他のホームページや書籍等に掲載されている内容を無断で使用しないための法律
他の人が書いたコンテンツの無断利用の他、生成AIが作成したコンテンツにも注意が必要
【参考:生成AI使用時の注意点】
ChatGPTを代表とする生成AIが発達し、短時間で文章をまとめることが容易にできるようになってきましたが、生成されたコンテンツの内容が間違うこともあれば、新しい情報には対応できていないこともあります。2024年4月に総務省・経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の中でも、日本でも著作権侵害などの倫理面含め今後どのように規制するか、又は規制しないのか対策に乗り出してきているという記述がなされています。
倫理的に問題なく、炎上する恐れがないか?
差別、誹謗中傷、法律・倫理に反する内容は倫理的に問題があるばかりか、稚拙な批判や誹謗中傷などを含む投稿が集中する「炎上」と呼ばれる現象を招きます。
炎上は、政治・宗教、性別(ジェンダー)、独りよがりな批判から発生しているケースが多々あり、一度炎上すると消すのは容易ではありません。
炎上に関するニュースをよく目にするようになりましたが、読み手の反応も多種多様です。炎上は、今までは人の心の中に留まり見えなかった『心理』がインターネットを通して『見える化』されたともいえますので、Webライティングの際はまず、読み手に配慮するという心がけが大切です。
Webライティング掲載時の対策
中立的・倫理的な文章を心がける
インターネット上に文章を掲載するWebライティングは、さまざまなユーザーが目にする可能性があります。そのため、誰かを傷つけたり、事実と異なる内容になっていないか、以下のことに十分配慮して文章を作成しましょう。
- 誇大表現をなくし、根拠を添えた文章にする
- 内容が正しいかどうかを調査の上掲載する
- 差別的、偏見的な表現を訂正する
自分がユーザーとして、してほしいことに立ち返る
ご自身が1人のユーザーとして商品・サービスを探す時の気持ちを振り返るのも、ユーザーに寄り添ったコンテンツ作成には役立ちます。
「何に不満だったか?」、「どんなことで『あ、これはいいな』と思ったのか」を振り返り、作成したコンテンツを見直してみましょう。
お客さまへのメリットを提示する
メリットを提示するのは、ホームページを見た時、お客さまにとって価値がある情報かどうかを瞬時に判断しやすくするためです。お客さまの関心を引き付けるだけでなく、購入行動につなげ、商品を気に入った時のリピート購入、良いクチコミ評価にもつながります。
今回はホームページにおけるWebライティングの注意点、対策について解説しました。
ホームページのコンテンツは、ビジネスオーナーの責任のもと掲載するものです。今回解説した「中立的・倫理的に」、「お客さまの立場にたち」、「お客さまへのメリットを」しっかり伝える内容にすることに加え、トレンドを見ながら変えていくことが重要です。それにより、コンテンツは単なる情報提供ではなく、お客さまに「これは自分に必要だ」と感じてもらう橋渡しの役割を果たします。さらに、お客さまとの信頼関係が築かれ、共感や購入行動を引き出すことができます。
本記事が「ホームページに掲載したコンテンツを公開した瞬間、世の中に出る」ことの認識と、ユーザーの探している情報の提供につながるコンテンツ作成のヒントとして読んでいただいた方のお役に立てれば嬉しいです。
NTTタウンページでは、ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」をご提供しています。
2019年のサービス提供開始以降、累計40,000件を超えるホームページを制作・運用し、個人事業主、中堅・中小企業をはじめとした多くのビジネスオーナーさまにご利用いただいてきました(2024年10月現在)。
これまで培ってきたNTTグループの知見とノウハウを活かして、多種多様なサービスと充実のサポート体制で、忙しいビジネスオーナーさまのホームページ制作から公開後の運用に至るまで、責任を持ってサポートいたします。

ホームページ制作・運用サービス「デジタルリード」の特長
特長①
ホームページ制作・運用はNTTグループの専門スタッフがフルサポート!
特長②
さまざまな目的のホームぺージ制作に対応、デザインも洗練!
特長③
ネットショップ・予約機能など、ホームページでの成約に導く充実機能多数!
ホームページは「制作して終わり」ではなく、その後の集客や売上アップなど目的とする「成果」につなげてこそ価値があります!
「インターネット・Webが苦手なのでサポートしてほしい…」
「競合に”勝てる”ホームページをめざしたい」
など、当社は全てのビジネスオーナーさまのホームページ活用に関するお悩み・課題に寄り添い支えます。
ぜひ、あなたのホームページの全てをお任せください!
・各ツール、サイトの情報は2024年12月現在タウンページ社調べのものです
・本記事に記載されている会社名、製品名、サービス名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。
ホームページの基礎知識に関連する記事